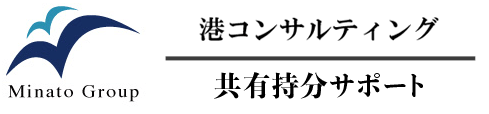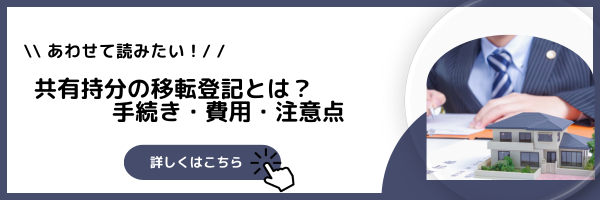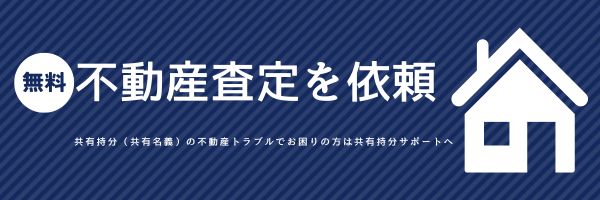-
共有名義から単独名義に変更・親子でスムーズな手続きを実現するには?

共有名義の不動産を、お子さんの単独名義に変更したいと考えていませんか。
相続や贈与を検討する際に、親子の間で不動産の名義変更は複雑な手続きを伴うため、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
今回は、共有名義から単独名義への変更手続きについて、親子間のよくあるケースや解決策、必要書類、費用、税金などを分かりやすくご紹介します。
スムーズな手続きを進めるための注意点も解説しますので、ぜひ最後までお読みください。
相続や贈与を検討されている40代以上の親世代の方にとって、役立つ情報となることを願っています。
共有名義から単独名義に変更・親子間のよくあるケースと解決策
生前贈与による単独名義への変更
親子で契約している共有名義不動産を、生前に親から子への贈与によって単独名義に
変更することも可能です。
この場合、贈与契約書を作成し、法務局で所有権移転登記の手続きを行う必要があります。
贈与税の課税対象となる可能性があります。贈与税の計算方法や税額を事前に確認し、必要に応じて税理士に相談しましょう。
贈与額によっては、税金対策として節税できる方法も検討できます。
相続による共有名義の解消方法
両親のどちらかが亡くなり、父または母と子へ不動産の相続が発生した場合、共有解消方法は大きく分けて4つあります。
その4つが『持分の売買、贈与、放棄、現物分割』です。
売買:自身の持分を共有者へ金銭を得て譲渡する方法
※相場価格より低い価格で取引すると贈与とみなされ、贈与税が発生する
可能性があります。
贈与:無償で持分を譲渡する方法
放棄:自分の持分を他の共有者に持分割合に応じて割り当てる方法
現物分割:共有不動産を分筆して、分筆された土地を共有者各々で単独で所有する方法
※分筆:登記簿上1つの土地を、複数に分割して登記し直す方法
親子間の意見の不一致への対処法
相続や贈与において、親子間で意見が一致しないケースも少なくありません。
話し合いが難航する場合は、まずはそれぞれの立場や考えを丁寧に聞き取り、共通の理解点を探ることから始めましょう。
それでも解決しない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な解決策を検討することをお勧めします。
また、持分のみを第三者に売却するという方法もあります。持分買い取りを専門にしている不動産会社へご相談ください。
単独名義への変更手続き・必要な書類と費用
贈与・売買・放棄それぞれの必要書類
いずれの場合も、不動産の登記簿謄本、登記権利者の住民票、登記義務者の印鑑証明書、固定資産評価証明書といった基本的な書類に加え、手続きの方法に応じて必要な書類が異なります。
贈与の場合は、贈与契約書、売買の場合は売買契約書、放棄の場合は内容証明郵便による意思表示などが挙げられます。
法務局のウェブサイトで必要な書類を確認するか、司法書士に相談して適切な書類を準備しましょう。
※登記権利者:持分を取得する人 登記義務者:持分を手放す人
各手続きにかかる費用と税金の種類
手続きにかかる費用は、司法書士への報酬、登録免許税、印紙税、不動産取得税、贈与税、譲渡所得税などです。
これらの税金は、不動産の価格や手続きの方法によって大きく変動します。
特に贈与税は、贈与額によって税率が異なるため、事前に税理士に相談して税額を正確に
把握しておくことが重要です。
司法書士への依頼と費用相場
司法書士への依頼は、手続きの複雑さや時間短縮のためにも有効です。
司法書士は、書類作成から登記申請までを代行し、手続きをスムーズに進めてくれます。
費用は、手続きの内容や司法書士事務所によって異なりますが、数万円から十数万円程度が相場です。
スムーズな手続きのための注意点
金融機関への事前相談の重要性
住宅ローンが残っている場合は、原則名義変更ができません。
金融機関に事前相談が必要です。
名義変更には金融機関の承諾が必要な場合があり、無断での名義変更は契約違反となる可能性があります。
事前に相談することで、手続きに必要な書類や手続きの流れ、注意点などを確認できます。
登記申請書の正確な記入方法
登記申請書は、専門的な知識が必要なため、誤った記入は手続きの遅延や却下につながる可能性があります。
自分で記入する場合、法務局のウェブサイトで様式を入手し、丁寧に記入しましょう。
不安な場合は、司法書士に依頼することをお勧めします。
専門家への相談
相続や贈与、売買、放棄など、不動産の名義変更には様々な方法があり、それぞれにメリット・デメリット、必要な書類、費用、税金などが異なります。
専門家である税理士や司法書士に相談することで、最適な方法を選択し、スムーズに手続きを進めることができます。
まとめ
共有名義から単独名義への変更手続きは、相続や贈与の方法、そして、売買や放棄といった選択肢など、様々な方法が存在し、それぞれに手続きや費用、税金が異なります。
親子間での円滑な手続きを進めるためには、事前に十分な情報収集と、税理士や司法書士などの専門家への相談が不可欠です。
この記事でご紹介した情報を参考に、ご自身の状況に最適な方法を選んでください。
編集者

-
不動産の共有名義による「相続」「離婚」「相続後」などの親族間トラブルを抱えている方は共有持分サポートへ。当社では弁護士、司法書士、不動産鑑定士、税理士などの専門分野のスタッフが共同で問題解決のために取り組むことで、素早い対応が可能となっております。
本社を置く大阪だけではなく、全国エリアをカバーしており、これまでも遠方にお住まいのお客様の問題解決を数多く対応させていただいた実績がございますので、どなたでもお気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 2025年6月29日共有持分コラム共有名義人が自己破産したら他の共有者への影響はどうなる?リスクと軽減策を解説!
- 2025年6月4日共有持分コラム共有不動産の放置・リスクと解決策?相続対策も解説
- 2025年5月29日不動産売却コラム共有名義で不動産売却できない時の対処法・解決策
- 2025年5月29日共有持分コラム共有持分を勝手に売却された時の法的根拠と対処法
共有持分不動産の問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
-
お電話での無料相談はこちら
-
-
無料相談はこちら
-
-
-
受付時間
-
10:00~20:00【年中無休】
-