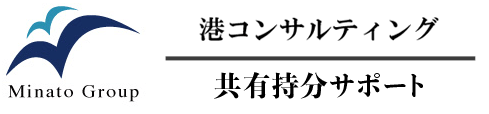-
共有名義不動産の固定資産税とは!滞納するとどうなるのかもあわせて解説!
共有名義不動産にかかる固定資産税では、たとえ自分が納税義務を果たしていても、他の共有者の滞納によって差し押さえ等のリスクが及ぶ可能性があります。これは単独名義にはない特徴でもあり、多くの方が誤解しやすいポイントです。
本記事では、共有名義不動産の固定資産税の仕組み、リスク、差し押さえの流れと対処法まで詳しく解説します。
□共有名義不動産の固定資産税の仕組みは?
共有名義不動産を所有している方の中には、「誰がいくら払うの?」「滞納したらどうなるの?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
まずは支払い方法の仕組みをご説明します。
*納税代表者
固定資産税は、不動産の共有者全員に納税義務がありますが、納税通知書は「納税管理人(代表者)」として選ばれた1名に送付されます。代表者が一括で納付したうえで、持分に応じて各共有者に費用を請求するのが一般的な流れです。
そのため、代表者の選出が必要となります。
代表者は以下の様な基準で自治体から選ばれることが多いです。
- 共有持分が一番多い人
- 不動産がある場所に住んでいる人
- 登記簿に記載している順番
また、自治体が決めた代表者ではなく、共有者全員で話し合い、代表者を決めて自治体に申し出ることも可能です。
*納付時期
支払い時期は単独名義と同様で、毎年4月~6月頃に自治体から納税通知書が送付されます。
自治体によって異なりますが、一般的には年4回の分割納付(6月、9月、12月、翌年2月)か、一括納付(4月~6月)を選択できます。
*連帯納付義務
共有名義不動産の固定資産税は、「共有者全員が責任を負う」、連帯納付義務が課せられます。
納税通知書は、共有名義人の中から選ばれた代表者のみへ送付されますが、納税義務は共有者全員にあり、代表者が支払わなくても、他の共有者にも請求がくることを覚えておきましょう。
□固定資産税を滞納するとどうなる?
固定資産税を滞納すると、納期限からの経過日数に応じて対応が変化していきます。
*延滞税
納期限を過ぎると、税額に対して延滞税(延滞金)が発生します。
延滞税の利率は毎年見直されており、2025年度(令和7年)に適用される年率は以下の通りです。
- 納期限の翌日から1カ月以内:年2.4%
- 納期限の翌日から1カ月を超えると:年8.7%
なお、制度上の上限はそれぞれ「年7.3%」「年14.6%」と定められていますが、実際に適用される利率は市中金利(特定基準割合)に基づいて決定されるため、現在はこれよりも低い水準になっています。
延滞税は日数に応じて日割りで加算されていくため、放置すればするほど金額が膨らみます。支払いが困難な場合でも、早めに自治体へ相談し、分納や猶予などの措置を検討することが重要です。
*督促状・催告書
固定資産税を滞納すると、督促状が納期限から20日以内に発せられます。
そのまま放置していると、納付の催告書が送られてきます。
この段階までくると、いよいよ差し押さえが視野に入ります。
*財産の差し押さえ
督促状や催告書の送付から10日経過しても納付に応じなかった場合、自治体は預貯金や給与、車などの資産を差し押さえることができます。また、不動産の差し押さえに繋がる可能性もあります。
共有名義不動産の場合、代表者だけでなく、他の共有者の財産も差し押さえの対象となる可能性があるため、注意が必要です。
このように固定資産税を滞納すると、さまざまなリスクがあります。
□固定資産税を滞納した時の対処法
滞納をしてしまい、どうしても現在支払いが難しいとなった場合は自治体へまずは相談をしてみましょう。
*分納の相談
固定資産税は通常一括納付か年4回の分割納付ですが、事前に支払いが難しいと相談することで分納を認めてもらえる可能性もあります。
*徴収猶予の確認
一定の条件(病気や事業の廃止や災害等)を満たすことにより、最大1年間の支払い猶予が認められる場合があります。
*換価の猶予
一時に納付することで生活の維持が困難になる恐れがあると認められた場合に、申請に基づいて差し押さえ財産の売却を一時的に猶予してもらえる制度もあります。
□共有名義不動産のリスク回避策
共有名義の不動産を所有し続けることは、固定資産税の滞納の恐れ以外にも、不動産の活用や処分に共有者全員の同意が必要となるため制約が多く発生し、トラブルのもとになります。可能であれば共有状態を解消することも検討しましょう。
*不動産の全体売却
不動産全体を売却し、共有関係を解消する方法です。共有者全員の同意が必要です。不動産が未活用状態で、全員の同意が取れる場合は最もスムーズな方法です。
*共有者へ持分売却
自分の持分を他の共有者に買い取ってもらうことで、自身は共有関係から抜ける方法です。市場価格に近い金額での売却になるため、共有者に十分な購入資金がない場合は買い取りが難しい可能性もあります。
*第三者に持分売却
自分の持分の売却であれば、共有者の同意は不要です。全体売却が難しく、共有関係から抜け出したい場合は、持分買取専門の不動産会社へ相談してみるのも1つの手段です。
まとめ
共有名義不動産の固定資産税は、共有者全員が責任を負う連帯納税義務があることを理解しておきましょう。
納税通知書は代表者へ送付されますが、納税義務は共有者全員にあります。
滞納すると、督促状、延滞金、差し押さえといった深刻なリスクに発展します。納期限を守ることはもちろん、問題が起きた場合は早期に自治体へ相談しましょう。
もし、共有関係による不安や負担が大きいと感じたら、持分売却や共有解消といった根本的な解決策を検討することも大切です。
編集者

-
不動産の共有名義による「相続」「離婚」「相続後」などの親族間トラブルを抱えている方は共有持分サポートへ。当社では弁護士、司法書士、不動産鑑定士、税理士などの専門分野のスタッフが共同で問題解決のために取り組むことで、素早い対応が可能となっております。
本社を置く大阪だけではなく、全国エリアをカバーしており、これまでも遠方にお住まいのお客様の問題解決を数多く対応させていただいた実績がございますので、どなたでもお気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 2025年6月29日共有持分コラム共有名義人が自己破産したら他の共有者への影響はどうなる?リスクと軽減策を解説!
- 2025年6月4日共有持分コラム共有不動産の放置・リスクと解決策?相続対策も解説
- 2025年5月29日不動産売却コラム共有名義で不動産売却できない時の対処法・解決策
- 2025年5月29日共有持分コラム共有持分を勝手に売却された時の法的根拠と対処法
共有持分不動産の問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
-
お電話での無料相談はこちら
-
-
無料相談はこちら
-
-
-
受付時間
-
10:00~20:00【年中無休】
-