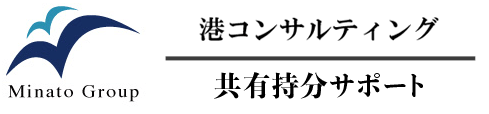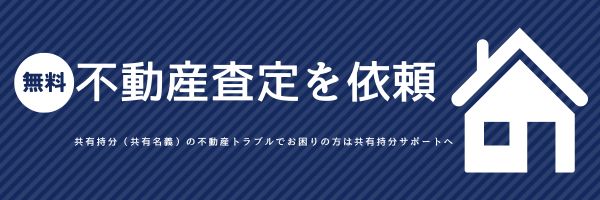-
共有名義人が自己破産したら他の共有者への影響はどうなる?リスクと軽減策を解説!
もし、共有名義人の一人が自己破産した場合、自分にどういった影響があるのか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか?
自己破産後の共有不動産の扱いや自身への影響、そして将来的なリスク軽減策としてどういったことができるのか?
今回は、共有不動産におけるリスクと対策に焦点を当て、具体的な事例を交えながら、それらの課題について考察します。
共有名義人の破産手続きどうなる
自己破産申立て後の基本的な流れ
共有名義人の一人が自己破産を申し立てると、裁判所は破産手続き開始を決定します。
この決定により、破産者(自己破産を申し立てた者)の財産は破産財団に組み入れられ、破産管財人が選任されるのが一般的です。
破産管財人は、破産者の財産を管理・処分し、債権者への配当を行います。
この手続きは、債権者の権利を保護し、破産者の経済的再生を支援することを目的としています。
破産手続きの期間は、ケースによって異なりますが、数ヶ月から数年かかることもあります。
共有不動産の法的扱いと他の共有者への影響
自己破産において、処分対象となるのは破産者本人の財産です。
共有名義不動産の場合、破産者の共有持分だけが処分対象となります。
不動産全体が処分されるわけではありません。
しかし、この共有持分の処分によって、残りの共有者にとって様々なリスクが生じる可能性があります。
例えば、破産者の持分が競売にかけられ、見知らぬ第三者が新たな共有者となる可能性があります。
これにより、不動産の管理や売却に関して、合意形成が難しくなるなどの問題が発生する可能性があります。
破産管財人による財産の処分の流れ
共有名義不動産も財産となるため、共有持分の価値を把握するため、不動産全体の評価額や持分割合、他共有者の意向調査(買取の意思があるか)などの確認を行い、処分方法を検討します。
具体的には、下記の処分方法を検討します。
・他の共有者へ持分の買い取りを提案
・第三者(持分専門の買取会社など)への共有持分の売却
・不動産全体を共有者と協力して売却(任意売却)
・共有者が買取も売却協力も拒否した場合、共有物分割請求訴訟を起こし、裁判所の判断で分割を行う
自己破産によって共有者へ影響が及ぶケース
共有不動産に住宅ローンの残債があり、抵当権が設定されている場合は複雑になります。
抵当権が設定されている場合
共有名義不動産全体に抵当権が設定されている場合、自己破産した共有者の持分だけでなく、他の共有者の持分にも影響が及ぶ可能性があります。
抵当権がある場合、その不動産は「担保権付財産」として扱われます。
この場合、破産管財人は勝手に処分(売却)できません。
まずは、抵当権者(金融機関)の動向が優先されます。
抵当権者は、不動産を競売にかけて債権を回収しようとする可能性があり、その場合、他の共有者も不動産を失う可能性があります。
競売を回避するためには、ローンを一括返済し抵当権を抹消するか、あるいは債権者と交渉し、返済条件の変更(ローンの借り換えなど)を行う必要があります。
または、共有者と協議の上、任意売却が提案されます。
連帯債務やペアローンがある場合
共有名義の不動産を購入する際に、連帯債務やペアローンを利用していた場合、破産した共有者の債務は、他の共有者が全額負担することになります。
連帯債務のリスクを軽減するためには、契約段階で連帯債務を回避する、あるいは連帯保証保険に加入するなどの対策が有効です。
リスク軽減のために取れる具体策
任意売却による対応
自己破産した共有者の持分が競売にかけられる前に、任意売却を行うことで、競売よりも高い価格で売却することができます。
債権者への配当を最大化することができ、競売よりも有効です。
また、競売となった場合は、情報が全国に公開されるため、プライバシーの問題も懸念材料となります。
任意売却は、通常の不動産売買に近いため、周りに知られることなく売却手続きが行えます。
管財人や金融機関との交渉が必要となるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
自己破産者の持分を他の共有者が買い取り
対象の共有不動産を手放したくない場合は、自己破産した共有者の持分を買い取ることで、第三者との共有状態を避け、不動産の管理・運営を円滑に行うことができます。
しかし、高額な資金が必要となるため、財務状況を慎重に検討する必要があります。
リースバックの活用可能性
不動産に住み続けたい場合、リースバックは、不動産を売却した後も引き続き利用できる制度です。
自己破産した共有者は、リースバックを活用することで、住居を確保しつつ、債務整理を進めることができます。
しかし、リースバックは家賃負担が発生するため、経済的な負担を十分に考慮する必要があります。
また、破産管財人の承認も必要となります。
任意売却等の他の手段の方が債権者への配当額が高くなる場合は却下される可能性もあります。
まとめ
共有名義人の自己破産は、多大な影響を与える可能性があります。
競売による不動産価値の低下、第三者との共有状態による管理運営の複雑化、さらには連帯債務による追加的な経済的負担など、様々なリスクが潜んでいます。
これらのリスクを軽減するためには、任意売却、持分買取、リースバックといった対策を検討し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。
早期の対応と適切なリスク管理が、将来的なトラブル回避に大きく貢献します。
【破産管財人・共有者の皆様へ】
共有不動産の処分や交渉に関して、専門的なサポートをお探しの方は、ご相談ください。
当社は共有名義の不動産買い取りを専門に行っております。
お気軽に当社にご連絡下さい。
編集者

-
不動産の共有名義による「相続」「離婚」「相続後」などの親族間トラブルを抱えている方は共有持分サポートへ。当社では弁護士、司法書士、不動産鑑定士、税理士などの専門分野のスタッフが共同で問題解決のために取り組むことで、素早い対応が可能となっております。
本社を置く大阪だけではなく、全国エリアをカバーしており、これまでも遠方にお住まいのお客様の問題解決を数多く対応させていただいた実績がございますので、どなたでもお気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 2025年6月29日共有持分コラム共有名義人が自己破産したら他の共有者への影響はどうなる?リスクと軽減策を解説!
- 2025年6月4日共有持分コラム共有不動産の放置・リスクと解決策?相続対策も解説
- 2025年5月29日不動産売却コラム共有名義で不動産売却できない時の対処法・解決策
- 2025年5月29日共有持分コラム共有持分を勝手に売却された時の法的根拠と対処法
共有持分不動産の問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
-
お電話での無料相談はこちら
-
-
無料相談はこちら
-
-
-
受付時間
-
10:00~20:00【年中無休】
-