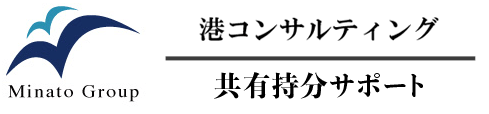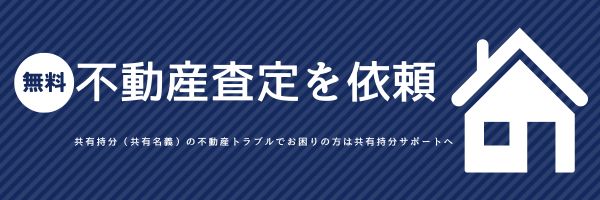-
離婚時の家の財産分与!共同名義の取り扱いのポイントについてわかりやすく解説

離婚を検討中の方にとって、財産分与は大きな悩みの種です。
特に、家などの不動産が夫婦共有名義になっている場合、その扱いをどうすれば良いのか、不安に感じられる方も多いのではないでしょうか。
離婚後の生活をスムーズに送るためにも、共有名義の家の財産分与について、正しい知識を身につけておくことが重要です。
今回は、離婚と財産分与、そして共有名義の家の扱い方について、分かりやすく解説します。
スムーズな離婚に向けて、ぜひ最後までお読みください。
離婚における財産分与と共同名義の家の扱い方
共同名義の家の持分割合と財産分与の関係
夫婦で家を共同名義で購入する際、それぞれの持分割合は、通常、購入時にそれぞれが出資した金額の割合で決定されます。
例えば、2,000万円の家を購入する際に、夫が1,800万円、妻が200万円を出資した場合、夫の持分割合は10分の9、妻の持分割合は10分の1となります。
しかし、この持分割合は、離婚時の財産分与の割合とは必ずしも一致しません。
離婚時の財産分与は、原則として夫婦間で2分の1ずつ分割されます。
これは、夫婦の財産形成への貢献度が同程度であるとみなされるためです。
たとえ、持分割合が夫10分の9、妻10分の1であっても、財産分与では、家の価値を2等分し、それぞれが半分ずつ取得することになります。
ただし、特別な事情がある場合は、この原則から外れることもあります。
裁判所が事情を考慮して、より公平な分割を行う可能性があります。
離婚後のトラブル発生リスクと予防策
離婚後も共有名義のままにしておくと、さまざまなトラブルが発生するリスクがあります。
・活用方法の意見が一致しない場合
売却やリフォームなど、不動産に関する重要な決定を行う際に、相手方の同意が必要になります。
意見が一致しない場合、手続きが滞ったり、深刻な紛争に発展したりする可能性があります。
・住宅ローンを組んでいる場合
共有者の片方がローンの返済を延滞した場合、金融機関から不動産を差押えられ、競売にかけられる可能性もあります。
・相続が発生した場合
元配偶者が亡くなった場合、その持分は相続人に移転し、新たな相続人との合意が必要になる為、売却や活用が困難になる可能性があります。
いずれにしても、離婚後も元夫(元妻)やその親族と連絡を取り続ける必要が発生します。
これらのトラブルを回避するためには、離婚時に共有名義を解消し、単独名義にするか、売却して代金を分割することが推奨されます。
共同名義の家の売却または名義変更とは?
共有名義のまま売却する場合の手続き
共有名義のまま家を売却する場合、売買契約には、夫婦双方の同意が必要です。
売却代金は、原則として夫婦で折半されます。
ただし、住宅ローンが残っている場合は、対応方法が異なります。
住宅ローンがある場合の対応
住宅ローンが残っている場合、財産分与はより複雑になります。
まず、ローンの残債額と不動産の価値を比較する必要があります。
ローンの残債額が不動産の価値を上回る「オーバーローン」の場合、不動産はマイナス価値となり、財産分与の対象とはなりません。
不動産の売却には、ローンを完済し、抵当権を抹消する必要があるため、共有名義を解消するためには、オーバーローンの残債分を自身の資金や親族からの援助等で一括返済する、もしくは金融機関と交渉し、任意売却をするかになります。
任意売却の場合は、売却代金をローン返済に充て、残りのローンは引き続き返済が必要です。
※任意売却:住宅ローンの返済が困難になった時などに、金融機関の同意を得て不動産を売却する債務整理の方法
一方、ローンの残債額が不動産の価値を下回る「アンダーローン」の場合、売却代金からローンの残債を支払った後、残りの金額を財産分与として分割します。
一方への名義変更手続きと代償金
共有名義から一方への単独名義に変更する場合、名義変更の手続きが必要です。
この手続きには、不動産登記が必要です。
通常、名義を取得する側は、相手方に家の価値の半額相当の代償金を支払います。
ただし、夫婦間の合意があれば、代償金の額の変更や、代償金なしで名義変更することも可能です。
住宅ローンがある場合の共有名義から単独名義への名義変更
住宅ローンの残債がある状態では、原則、名義変更はできません。
契約違反の恐れがあるため、金融機関への相談と承諾が必要です。
対応方法としては、金融機関へ債務引受(債務を引受人へ移転する契約)の相談、または、売却時と同様、ローンを一括返済し、単独名義に変更する方法があります。
または、居住する側が新しいローンに借り換えし、住宅ローンを完済し単独名義に変更するといった方法もあります。
自分の持分のみの売却
共有者と意見が一致せず、共有名義を解消出来ない場合は、自身の持分のみを第三者に売却し、共有名義を解消するという方法もあります。
例えば、どちらか一方だけそのまま居住する為、自身の持分を居住する共有者に引渡し、代償金を支払ってもらいたいが拒否された場合です。
こういった場合に、第三者への持分の売却も検討できます。
※住宅ローンが残っている場合は、抵当権の設定がある為、売却は難しい可能性が高いです。
残債が残り僅かで完済できる場合は、買取可能な場合もあります。
離婚における財産分与の種類と手続き
協議離婚と調停離婚での財産分与
協議離婚とは、夫婦間で話し合って離婚条件を決める方法です。
財産分与についても、合意に基づいて分割方法を決定します。
合意が成立すれば、スムーズに離婚手続きを進めることができます。
しかし、話し合いがまとまらない場合は、調停離婚を検討する必要があります。
調停離婚では、裁判所の調停委員が介入し、夫婦間の合意形成を支援します。
調停委員の助言や提案を参考に、双方が納得できる解決策を見つけることができます。
裁判離婚における財産分与
協議離婚や調停離婚で合意が成立しない場合は、裁判離婚となります。
裁判離婚では、裁判官が財産分与の割合を決定します。
裁判官は、夫婦の年齢、収入、貢献度、生活状況などを考慮して、公平な分割を目指します。
裁判離婚は時間と費用がかかるため、なるべく協議離婚や調停離婚で解決することを目指すことが重要です。
財産分与における専門家への相談
離婚は複雑な問題を伴うため、弁護士や司法書士などの専門家への相談が非常に役立ちます。
専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、スムーズな離婚手続きをサポートします。
特に、財産分与については、専門家の助言を得ることで、自身の権利を守り、不利な条件を回避することができます。
複雑な状況や不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
売却手続きには不動産会社が関与します。 売却前に不動産の査定を行い、適正な価格で売却できるようサポートします。
まとめ
離婚に伴う共同名義の家の財産分与は、持分割合とは関係なく、原則として夫婦で半分ずつ分割されます。
しかし、住宅ローンや相続などの要素によって、手続きは複雑になる可能性があります。
離婚後も共有名義のままにしておくと、売却やリフォームなどの際に相手方の同意が必要となり、トラブルに発展する可能性が高まります。
そのため、離婚時には共有名義を解消し、単独名義にするか、売却して代金を分割することが望ましいです。
協議離婚が理想ですが、調停や裁判といった手段も存在します。
それぞれの状況に合わせて、最適な解決策を選択することが重要です。
財産分与に関する手続きは、専門家の助言を得ながら慎重に進めることを強く推奨します。
早めの準備と適切な対応によって、離婚後の生活をスムーズに始めることができます。
編集者

-
不動産の共有名義による「相続」「離婚」「相続後」などの親族間トラブルを抱えている方は共有持分サポートへ。当社では弁護士、司法書士、不動産鑑定士、税理士などの専門分野のスタッフが共同で問題解決のために取り組むことで、素早い対応が可能となっております。
本社を置く大阪だけではなく、全国エリアをカバーしており、これまでも遠方にお住まいのお客様の問題解決を数多く対応させていただいた実績がございますので、どなたでもお気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 2025年12月20日共有持分コラム自分に最適な手段を見つける!共有不動産を現金化する方法を解説
- 2025年11月20日相続コラム相続登記義務化と共有持分の影響!罰則内容と登記手続きの変更点を解説
- 2025年11月5日共有持分コラム持分放棄することと登記変更のステップとコスト解説
- 2025年10月20日登記コラム未登記建物の売買契約と必要書類とは?手続き費用も解説
共有持分不動産の問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
-
お電話での無料相談はこちら
-
-
無料相談はこちら
-
-
-
受付時間
-
10:00~20:00【年中無休】
-