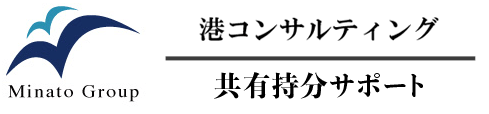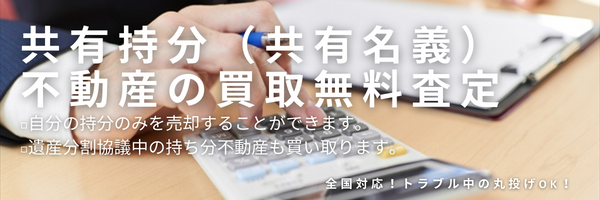-
不動産トラブル!私道の共有持分で揉めないための対策についてわかりやすく解説

私道は、個人が所有・管理する道路です。
多くは分譲住宅地などで見られますが、その共有持分を巡るトラブルは少なくありません。
隣家との関係、将来的な売買、そして法律的な知識など、不安要素は多岐に渡ります。
今回は、私道共有持分に関するトラブルの種類、解決策、そして予防策について、分かりやすく解説します。
不動産売買の際の注意点も合わせてご紹介します。
私道の共有持分の基礎知識
私道と公道の違い
私道は個人や法人が所有・管理する道路、公道は国や地方自治体が管理する道路です。
私道は所有者の許可なく通行できませんが、公道は誰でも通行できます。
道路の修繕も、私道は所有者、公道は国や自治体が責任を負います。
道路交通法も、原則として私道には適用されません。
ただし、建築基準法上の道路に該当する位置指定道路や42条2項道路は公道と同様に扱われる場合があります。
※位置指定道路:特定行政庁から道路位置指定を受けた私道
※42条2項道路:1950年の建築基準法が定められる前からあった幅員4メートル未満の道路
共有私道の種類
共有私道には、大きく分けて「共同所有型」と「相互持合型」の2種類があります。
それぞれの権利関係は異なります。
1.共同所有型
1本の私道を複数の所有者が共有する形態です。
私道全体に対して、各自で所有している敷地面積に応じて持分が決まるのが特徴です。
所有の権利は私道全体になるため、通行するだけであれば他の共有者から承諾を得る必要はありません。
ただし、変更行為に関しては共有者全員の同意が必要になります。
管理行為は持分の過半数の同意が必要。保存行為は単独で行えます。
ただし、2023年4月の民法改正により、軽微な変更は持分の過半数の同意で可能になりました。
※変更:道路の採掘工事
※軽微変更:砂利道だった私道をアスファルト舗装にする等
※管理:全面再舗装、樹木の伐採など
※保存:メンテナンス(掃除など)
2.相互持合型
私道を複数の区画に分割し、それぞれが独立した所有権を持つ形態です。
共有者の許可を得ずに、自身の所有している私道の管理が行えます。
ただし、私道に対して持っている権利は部分的になります。
その為、他の方が所有している道を通行するには、その所有者から承諾が必要です(通行地役権)。
また、排水管などの採掘工事が必要な場合、隣接する所有者の許可が必要です。
私道共有持分の権利関係の確認方法
私道共有持分の権利関係を確認するには、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得するのが確実です。
地番を特定し、申請することで、所有者や持分比率などの詳細な情報を得ることができます。
インターネットからも申請可能です。
私道の共有持分で発生しやすいトラブル
管理方法の不一致
共同所有型の私道では、管理方法について共有者間で意見が一致しないことがトラブルの原因となります。
例えば、舗装の要不要、修繕方法、費用負担など、意見が対立し、合意形成が困難になるケースがあります。
費用負担の問題:固定資産税や修繕費用
私道の維持管理には、固定資産税や修繕費用などの費用負担が伴います。
共有者全員が公平に負担するのが原則ですが、一部の共有者が費用を滞納するケースがあります。
滞納が続くと、他の共有者に負担が偏ったり、法的措置を検討せざるを得ない状況に陥ることもあります。
民法では、1年以内に費用を負担しない共有者の持分を、他の共有者が償金を支払うことで取得できる規定があります。
共有者との連絡が取れない場合
共有者の一人が行方不明になったり、連絡が取れなくなったりすることも、トラブルの原因となります。
連絡が取れない場合、私道の管理や修繕、売買などの意思決定が滞ってしまう可能性があります。
民法改正により、裁判所の許可を得れば、行方不明者の持分を除外して手続きを進めることが可能になりました。
私道共有持分トラブル事例と解決策
具体的なトラブル事例としては、隣地との境界線問題、通行権の侵害、私道内の駐車問題などが挙げられます。
解決策としては、まず共有者間での話し合いが重要です。
話し合いが不調に終わった場合は、行政への相談、弁護士への相談、調停・訴訟といった手段も考えられます。
私道における共有持分トラブルの解決策と予防策
共有者間での話し合い
トラブル発生時は、まず共有者間で話し合いを行い、合意形成を目指しましょう。
話し合いを行う際には、冷静に事実関係を確認し、それぞれの立場を理解することが大切です。
弁護士に相談し、話し合いの進め方や法的根拠を事前に確認しておくのも有効です。
行政への相談
話し合いが不調に終わった場合、市区町村役場などに相談してみましょう。
建築基準法上の道路であれば、行政が介入できる可能性があります。
また、専門機関による仲介を依頼できる場合があります。
弁護士への相談
法律的な知識が必要な場合、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、権利関係の確認、解決策の提案、交渉・訴訟代理など、さまざまなサポートをしてくれます。
裁判による解決
話し合い、行政への相談、弁護士への相談でも解決しない場合は、裁判による解決を検討する必要があります。
裁判は費用と時間がかかるため、最終手段として捉えるべきです。
不動産買取会社への相談
共有者との関係を完全に断ち切りたい場合、不動産買取会社に相談するのも一つの方法です。
買取会社であれば、私道を含む不動産をまとめて買い取ってくれるため、今後のトラブルから解放されます。
トラブル予防のための契約書作成と確認
トラブルを未然に防ぐためには、私道に関する権利関係を明確に記述した契約書を作成・確認することが重要です。
通行権、掘削権、費用負担、管理方法などを具体的に記載し、共有者全員で合意する必要があります。
近隣住民との良好な関係構築
私道は、近隣住民との共有物であることが多いです。
良好な関係を維持することで、トラブル発生を予防し、発生した場合でも円滑に解決できる可能性が高まります。
定期的なコミュニケーションを心がけましょう。
私道に接する不動産の売買に関する注意点
私道に接する不動産の売買では、私道の権利関係、維持管理費用、将来的なトラブルリスクなどを考慮する必要があります。
購入前に、法務局で登記簿謄本を取得し、権利関係をしっかり確認しましょう。
また、周辺住民に聞き込みを行い、過去のトラブルや潜在的なリスクがないかを確認することも大切です。
売買契約書には、私道に関する事項を明確に記載する必要があります。
まとめ
私道共有持分は、管理方法、費用負担、連絡不能など、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。
トラブルを未然に防ぐためには、権利関係の確認、契約書の作成、近隣住民との良好な関係構築が重要です。
トラブルが発生した場合には、話し合い、行政への相談、弁護士への相談、裁判、不動産買取会社への相談など、さまざまな解決策があります。
自身の状況に合わせて適切な手段を選択し、迅速に対応することが大切です。
私道に接する不動産の売買を検討する際には、私道の権利関係を十分に確認し、トラブルリスクを考慮することが不可欠です。
民法改正による影響も考慮に入れ、最新の法制度に基づいた対応を心がけましょう。
専門家への相談を早期に行うことで、より円滑な解決に繋がる可能性が高まります。
編集者

-
不動産の共有名義による「相続」「離婚」「相続後」などの親族間トラブルを抱えている方は共有持分サポートへ。当社では弁護士、司法書士、不動産鑑定士、税理士などの専門分野のスタッフが共同で問題解決のために取り組むことで、素早い対応が可能となっております。
本社を置く大阪だけではなく、全国エリアをカバーしており、これまでも遠方にお住まいのお客様の問題解決を数多く対応させていただいた実績がございますので、どなたでもお気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 2026年1月5日相続コラム土地の相続税が払えない場合どうなる?延納や物納制度と土地売却の活用法
- 2025年12月20日共有持分コラム自分に最適な手段を見つける!共有不動産を現金化する方法を解説
- 2025年11月20日相続コラム相続登記義務化と共有持分の影響!罰則内容と登記手続きの変更点を解説
- 2025年11月5日共有持分コラム持分放棄することと登記変更のステップとコスト解説
共有持分不動産の問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
-
お電話での無料相談はこちら
-
-
無料相談はこちら
-
-
-
受付時間
-
10:00~20:00【年中無休】
-