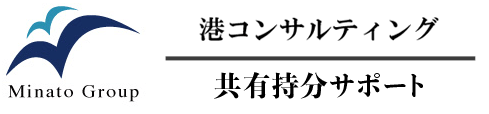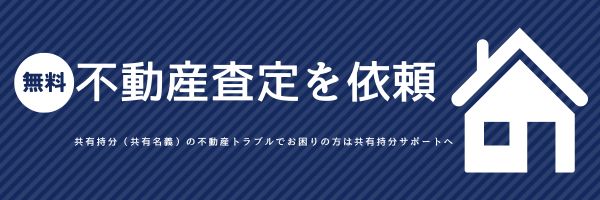-
共有名義の不動産で得た家賃収入はどのように分配するべき?解説します!
共有名義の不動産はメリットもデメリットも持ち合わせています。
一般的な不動産においてもトラブルに発展しないための対応が求められますが、家賃収入を得ている不動産を共有する場合、より多くの決定事項を話し合う必要があるのです。
今回は共有名義の不動産と、共有名義の不動産における家賃収入の分配について解説します。
共有名義の不動産とは?

共有名義の不動産とは、複数の名義人が持分を持ち、その所有権を共有している不動産のことです。
以下で共有名義の不動産について、不動産を所有するケースとメリット・デメリットとともに解説します。
共有名義不動産の基本概念
共有名義不動産は、複数の人々が所有権を共有する不動産を指します。
この形態は、経済的負担を分散し、共有者の間で効率的な利用を可能にします。
共有名義の不動産を所有するケース
共有名義の不動産を所有するケースは、主に以下の場面が考えられます。
・親が亡くなり、遺産として子どもたちに不動産が相続される。
・夫婦が共同で住宅を購入する。
・事業用の不動産を複数の会社が共同で購入する。
メリットとデメリット
共有名義の不動産を所有することにはメリットもありますが、デメリットもあります。
両方を照らし合わせて、不動産の今後について考えることが重要です。
メリット
・節税効果
共有名義不動産は、住宅ローン控除や特別控除など、複数の税金を節税できるというメリットを享受可能です。
共有者は個々の税負担を軽減できます。
・負担の分散
共有名義では、修繕費や固定資産税などの経費を共有者間で分担するため、一人当たりの負担が軽減されます。
・管理の効率化
物件の管理やメンテナンスを共有者間で分担することで、労力と時間の節約が可能になります。
デメリット
・意思決定の複雑さ
共有者全員の合意が必要な場合が多く、自身の希望がいつまでも通らない恐れがあります。
不動産の売却だけではなく、大きなリフォームを行うときも注意が必要です。
・トラブルのリスク
共有者間で意見の不一致が生じると、解決までに時間と労力がかかり、
最悪の場合、法的な争いに発展する可能性もあります。
・流動性の制限
共有名義の不動産は、一方の共有者が売却を希望しても、他の共有者の同意が必要となるため、
不動産の売却が困難になることがあります。
家賃収入の分配はどうする?
共有名義の不動産から家賃収入を適切に分配することは、共有者間の調和を保つ上で非常に重要です。
分配方法だけではなく、税務申告についても理解しておきましょう。
家賃収入の分配方法
家賃収入の分配は、通常、共有者の持分比率に基づいて行われます。
例えば、持分が半分ずつの場合、家賃収入も半分ずつに分配されます。
しかし、管理費用や修繕費など、特定の負担を担っている共有者には、追加の配分が考慮される場合もあります。
税務申告
共有名義不動産からの収入は、各共有者が個別に税務申告を行う必要があります。
家賃収入の総額から必要経費を差し引いた後、持分比に応じた所得を計算し、その所得に基づいて申告します。
税務処理
家賃収入に関する税務処理は複雑であり、適切な知識が必要です。
共有者が個々に管理する場合と、代表者を選出して集中管理する場合の両方があります。
どちらの方法を選択するにしても、透明性のある管理と定期的な報告が必要です。
トラブルを回避するためには
共有名義不動産におけるトラブルは、家賃収入の分配や管理に関連する問題が多く発生します。
トラブルを回避するためにも以下のポイントを押さえておきましょう。
管理者の選定
共有者間の信頼関係を維持するためにも、共有名義の不動産の管理者を選定することがおすすめです。
管理者は、家賃の収集や修繕計画の策定、共有者への定期的な報告など、多くの責任を担いますが、共有者間の調和を保ち、トラブルを未然に防ぐことにつながります。
家賃収入の公平な分配
家賃収入の分配に関するトラブルは、共有名義の不動産において最も一般的な問題です。
公平な分配を保証するためには、持分比率に基づいた明確な分配計画を策定し、必要に応じて管理者に追加の報酬を支払うと良いでしょう。
円滑なコミュニケーション、事前に合意を得ておくことでよくあるトラブルも回避できます。
修繕費や税金の公平な負担
共有者間で修繕費や税金の負担をどのように分担するかは、家賃収入と同じくしばしば議論になります。
負担の公平性を保つためには、持分比率に基づいた分担計画を立て、大規模な修繕には全員の合意を得ておくことをおすすめします。
また、管理者への経費に関する決定権を委任することで、意思決定の効率化が図れるでしょう。
まとめ

今回は共有名義の不動産と、共有名義の不動産における家賃収入について解説しました。
共有名義の不動産においては共有者間の合意が不可欠です。
合意を得られるような良好な関係性を築くためにも、管理者を選定したり、事前に家賃収入や修繕費の分担を決めておいたりすることをおすすめします。
よくある質問
Q1.共有者の1人が家賃を独占するのは違法?
はい、違法になる可能性があります。共有者全員に利益を分けなければならない義務があり、独占している場合は他の共有者が請求できます。
Q2.家族間で共有している不動産に家賃がある場合の注意点は?
家族だからといって口約束だけで分配を決めるのはNG。税務上のトラブルを避けるためにも、書面や記録に残すことが重要です。
Q3.共有名義の不動産で家賃収入をもらっていない場合でも申告は必要?
実際に収入を受け取っていない場合でも、持分がある限り所得が「ある」とみなされるケースがあります。ほかの共有者が家賃を全額受け取っていると、未申告による課税リスクもあるため、状況に応じて税理士に相談するのが安心です。
Q4.共有名義の家賃収入を不公平に配分された場合、どう対処すれば?
まずは共有者間で話し合いましょう。それでも解決しない場合、民事調停や訴訟も検討されます。証拠として通帳や契約書などを保存しておくことが重要です。不公平配分は法的トラブルにつながるため、事前に取り決めをしておくと安心です。
Q5.共有名義の家賃収入に関するトラブルを防ぐには?
トラブルを防ぐには、持分割合に応じた分配ルールを明確にしておくことが重要です。分配方法を文書化し、家賃管理は代表者の口座ではなく、専用口座での管理がおすすめです。税金・分配・契約内容を透明化することが信頼関係のカギになります。
編集者

-
不動産の共有名義による「相続」「離婚」「相続後」などの親族間トラブルを抱えている方は共有持分サポートへ。当社では弁護士、司法書士、不動産鑑定士、税理士などの専門分野のスタッフが共同で問題解決のために取り組むことで、素早い対応が可能となっております。
本社を置く大阪だけではなく、全国エリアをカバーしており、これまでも遠方にお住まいのお客様の問題解決を数多く対応させていただいた実績がございますので、どなたでもお気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 2026年2月20日共有持分コラム共有不動産の査定で見るポイントとは?価値を決める要因を解説
- 2026年2月5日共有持分コラム共有名義の不動産で片方が死亡したら誰が相続する?
- 2026年1月5日相続コラム土地の相続税が払えない場合どうなる?延納や物納制度と土地売却の活用法
- 2025年12月20日共有持分コラム自分に最適な手段を見つける!共有不動産を現金化する方法を解説
共有持分不動産の問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
-
お電話での無料相談はこちら
-
-
無料相談はこちら
-
-
-
受付時間
-
10:00~20:00【年中無休】
-