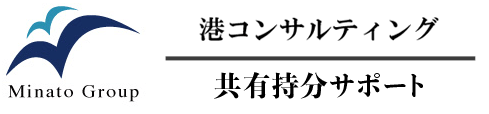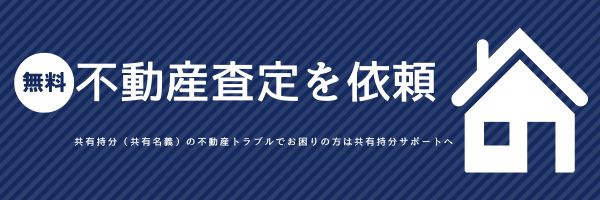-
共有持分でよくあるトラブルとは|具体例と解決方法

共有持分のトラブルは、不動産に関する深刻な問題として、多くの人が頭を悩ませています。
特に、相続や離婚などによって発生するトラブルが非常に多く、関係者の間で深刻な対立に発展することも少なくありません。
共有持分によって発生するトラブルは、不動産の利用や売却、相続、さらには費用負担など、様々な場面で起こり得ます。
本記事では、共有持分に関するトラブル事例、その解決方法について解説していきます。
共有持分のトラブルに悩んでいる、解決策を探しているあなたは、ぜひ最後まで読んでみてください。
共有持分とは?
共有持分とは、不動産を複数人で所有する形態のことを指します。
単独所有とは異なり共有不動産では、複数の所有者がそれぞれ持分比率に応じて不動産の権利を有しています。
共有持分が生まれる原因は様々です。
不動産の共同購入
複数人で資金を出し合って不動産を購入する場合、共有持分が発生します。
例えば、兄弟姉妹が共同で住宅を購入する場合や友人同士で投資目的で不動産を購入する場合などが挙げられます。
不動産の贈与
不動産を複数人に贈与する場合、共有持分が発生します。
例えば、親が子供たちに不動産を贈与する場合、子供たちが共有持分を持つことになります。
相続
不動産を複数人で相続する場合、共有持分が発生します。
例えば、両親が亡くなった場合、子供が共有で不動産を相続することになります。
共有不動産は、税制上のメリットや公平な分割ができるなど、魅力的な側面も持ち合わせています。
しかし、一方で共有不動産は、様々なトラブルを生み出す可能性も孕んでいます。
共有持分でよくあるトラブル
共有不動産では、様々なトラブルが発生する可能性があります。
ここでは、よくあるトラブルを具体的に見ていきましょう。
共有者間で意見がまとまらない
共有不動産の売却や賃貸、処分など行う場合は、共有者全員の同意が必要となります。
共有者全員の意見が一致せず、未活用の状態のまま保有しているというケースも多くあります。
夫婦が離婚する場合
夫婦共有名義で不動産を購入していた場合、共有不動産の所有権や住宅ローンの返済、固定資産税の支払い等、話し合いが必要となります。
特に離婚後も共有名義のまま保有し続けた場合、お互い連絡を取り続ける必要性があることや、後々、不動産を活用(売却等)したい場合や相続が発生した際に、トラブルに発展する可能性があります。
共有者の一部が行方不明で連絡が取れない
共有者の一部が行方不明になっていることで連絡が取れず、売却するにも同意を得られない状態です。共有者が行方不明の場合の対応としては、不在者財産管理人制度や失踪宣告などを活用する方法がありますが、時間や手続きが面倒でそのままになっているケースも多く見られます。
共有者が亡くなり、権利関係が複雑化している
共有者が亡くなると、その共有持分は相続人に引き継がれます。
相続人が複数いる場合、相続手続きが複雑化するだけでなく、相続人同士で意見が対立する可能性もありトラブルに発展する可能性があります。
また、遠縁の親戚と共有状態になり連絡先が分からないといったケースもあります。
費用負担に関するトラブル
共有不動産の維持費や修繕費などの費用負担について、共有者間で意見が一致しない場合、トラブルが発生することがあります。
また、収益物件として活用している場合、賃貸収入が正しく配当されず、共有者間で揉めるケースもあります。
共有持分トラブルの解決方法
共有持分のトラブルを解決するには、様々な方法があります。
共有不動産の全体売却
共有者同士で話し合いを行い、共有不動産を全体売却する方法です。
共有者全員が合意できれば、最もシンプルで費用対効果の高い解決方法と言えます。
自分の持分の売却
自分の持分を他の共有者に買い取ってもらうか、第三者(買取会社)へ売却する方法です。
自分の共有持分を売却する場合は、共有者全員の同意が不要となります。
全員の合意を得ることが困難な場合は、自分の持分を売却し共有状態から抜けるのも有効です。
共有持分の放棄
共有持分を放棄する方法です。
共有持分を放棄する場合、共有者全員に放棄する旨の意思表示を行います。
この意思表示は、内容証明郵便で行うようにしましょう。
放棄も共有者の同意は不要ですが、登記の際に他の共有者の協力が必要です。
共有物分割請求訴訟
共有者間で話し合いがまとまらない場合、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起することができます。
共有物分割請求訴訟では、裁判所が共有不動産の分割方法や分配方法を決定します。そのため、分割方法は自分の意思通りになるとは限りません。
まとめ
共有持分は、税制上のメリットや公平な分割ができるなど、魅力的な側面を持つ一方で、トラブル発生のリスクが高い側面も持ち合わせています。
共有持分のトラブルを解決するためには、共有者同士で話し合い、全体売却や自分の持分の売却、共有持分の放棄、共有物分割請求訴訟などの方法が考えられます。
共有者間で意見がまとまらずお困りの方へ
ご自身の持分売却であれば、共有者の同意は不要です。
当社は、共有持分の買取専門の不動産会社です。悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。
編集者

-
不動産の共有名義による「相続」「離婚」「相続後」などの親族間トラブルを抱えている方は共有持分サポートへ。当社では弁護士、司法書士、不動産鑑定士、税理士などの専門分野のスタッフが共同で問題解決のために取り組むことで、素早い対応が可能となっております。
本社を置く大阪だけではなく、全国エリアをカバーしており、これまでも遠方にお住まいのお客様の問題解決を数多く対応させていただいた実績がございますので、どなたでもお気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 2026年2月20日共有持分コラム共有不動産の査定で見るポイントとは?価値を決める要因を解説
- 2026年2月5日共有持分コラム共有名義の不動産で片方が死亡したら誰が相続する?
- 2026年1月5日相続コラム土地の相続税が払えない場合どうなる?延納や物納制度と土地売却の活用法
- 2025年12月20日共有持分コラム自分に最適な手段を見つける!共有不動産を現金化する方法を解説
共有持分不動産の問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
-
お電話での無料相談はこちら
-
-
無料相談はこちら
-
-
-
受付時間
-
10:00~20:00【年中無休】
-