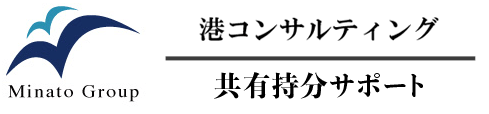-
共有特分の相続登記が義務化された影響と手続き方法
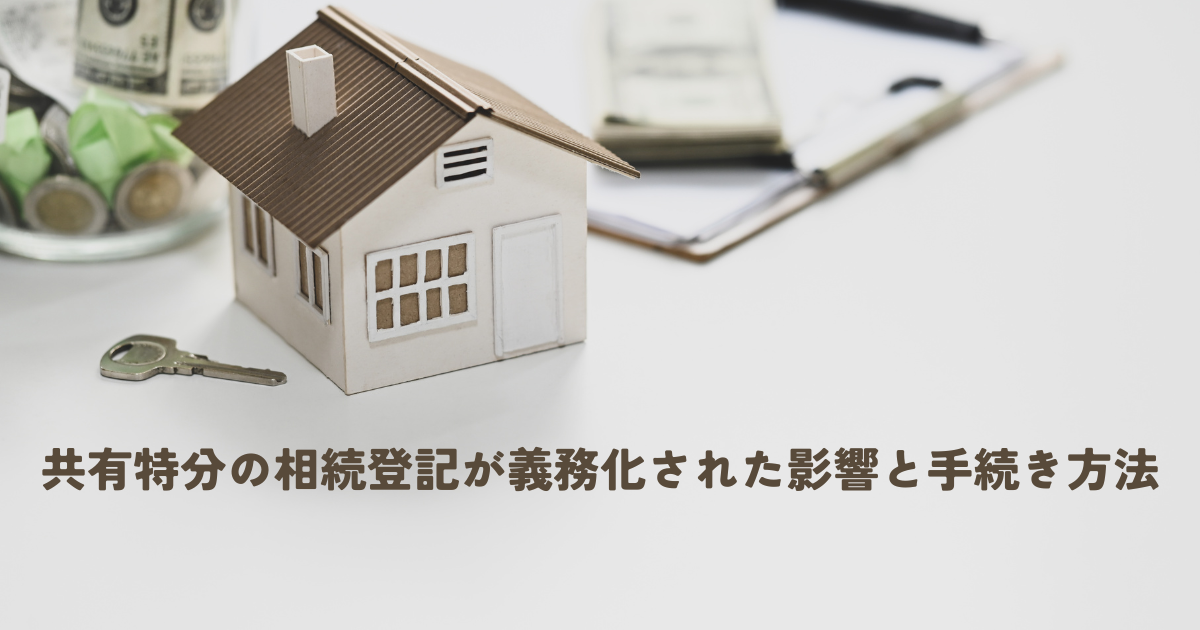
共有不動産の相続を経験された方、またはこれから経験される方にとって、相続登記義務化は大きな関心事でしょう。
特に、共有特分の相続登記については、手続きの複雑さや、それによって生じるリスクが未知数であるため、不安を抱かれる方も多いのではないでしょうか。
今回は、共有特分の相続登記義務化の概要、手続き、そして怠った場合のリスクについて、具体的な事例を交えながら解説します。
共有特分の相続登記義務化の概要
相続登記義務化の背景と目的
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
これは、相続によって不動産の所有権が移転した場合、相続人が所有権の登記を申請することが義務付けられたことを意味します。
その背景には、相続登記の未登記件数の多さが挙げられます。
未登記状態が続くと、所有権の所在が不明確となり、不動産の売買や担保設定といった取引が困難になったり、相続人間で紛争が発生するリスクが高まったりするといった問題が生じます。
そのため、所有権の明確化を図り、社会全体の取引の安全性を高めることを目的として、相続登記の義務化が施行されました。
これは、将来発生する可能性のある相続トラブルを未然に防ぎ、社会全体の安心安全に貢献する取り組みと言えます。
対象となる不動産と相続人
相続登記の義務化の対象となるのは、土地や建物といった不動産です。
相続人が単独で所有する不動産だけでなく、複数人で共有する不動産も対象となります。
共有不動産の場合、相続人全員が登記申請を行う必要があります。
相続人は、被相続人から相続権を有する者であり、法定相続人や遺言で相続人として指定された者が該当します。
亡くなった方の不動産を相続し、その所有権を登記簿に反映させることが義務付けられています。
相続人の範囲や権利関係は、民法や遺言書によって決定されますので、相続が発生した際には、まず相続人と相続財産を正確に確定することが重要です。
その後、相続人全員で遺産分割協議を行い、共有持分の割合を決定し、登記手続きに進むこととなります。
登記簿に正確な持分の記載がされることは、後の不動産売買や相続発生時のトラブルを防ぐために非常に重要です。
共有特分の相続登記の手続き
相続登記に必要な書類と手続きの流れ
共有特分の相続登記には、相続人の戸籍謄本、被相続人の死亡証明書、不動産の登記事項証明書などが必要となります。
手続きの流れとしては、まず必要書類を準備し、法務局に登記申請書を提出します。
その後、法務局による審査が行われ、問題なければ登記が完了します。
ただし、相続人の人数が多い場合や、相続財産に複雑な事情がある場合は、専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。
司法書士は、登記申請に必要な書類作成から申請手続きまでを代行してくれます。
相続人が複数いる場合の登記手続き
相続人が複数いる場合、相続人全員の合意を得て登記申請を行う必要があります。
全員の署名・押印が必要となるため、相続人間での協議が不可欠です。
相続人同士の意見が一致しない場合、遺産分割協議書を作成する必要があるかもしれません。
この協議書には、相続人全員の合意内容が明確に記載されなければなりません。
協議が難航する場合は、家庭裁判所での調停や審判を検討する必要もあるでしょう。
複数相続人の場合、手続きが複雑化し、時間と費用も増加する可能性があります。
相続登記の費用と期間
相続登記にかかる費用は、登録免許税や司法書士への報酬などです。
登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%で算出されます。
司法書士への報酬は、依頼する司法書士によって異なりますが、一般的に数万円から数十万円程度です。
手続き期間は、書類の準備や申請から登記完了まで、数ヶ月かかることが一般的です。
ただし、相続人の人数や状況、法務局の混雑状況によって、期間は変動します。
共有特分の相続登記をしないとどうなるか?
相続登記義務化による罰則
相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
これは、相続登記義務化に伴う罰則です。
ただし、正当な理由なく登記を怠った場合に科されるものであり、やむを得ない事情がある場合は免除される可能性があります。
それでも、罰金よりも、未登記状態によって生じる様々なリスクの方がはるかに大きいです。
登記を怠ることによるリスク(売却時の問題など)
登記を怠ると、不動産の売却や担保設定が困難になります。
また、相続人間で所有権に関する紛争が発生する可能性も高まります。
例えば、相続人が複数いる場合、登記されていないと、どの相続人が何%の持分を所有しているのかが明確ではなく、売却時にトラブルに発展する可能性があります。
共有不動産の売却を検討している場合、登記は必須です。
義務化後のトラブル事例と対応策
相続登記の義務化により、相続人は正当な理由がない限り、被相続人の死亡を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。
しかし、共有者が反対をしていたり、相続人と連絡が取れなかったり、相続人の所在が不明な場合、手続きが進まないといったリスクもあります。
このような場合、家庭裁判所への申立てなど、法的措置が必要となる可能性があります。
トラブルを未然に防ぐためには、相続発生後速やかに相続手続きを進め、専門家である司法書士などに相談することが重要です。
まとめ
今回は、共有特分の相続登記義務化の概要、手続き、そして登記を怠った場合のリスクについて解説しました。
共有不動産の相続は、手続きが複雑で、相続人同士の合意形成も必要となるため、専門家のサポートを受けることが重要です。
早期に手続きを進めることで、トラブルを回避し、円滑な相続を進めることができるでしょう。
また、共有名義不動産の売却をご検討でしたら、当社は共有名義不動産の買い取りを専門に行っている不動産会社です。
相続登記前であれば、売却に合わせて登記手続きもサポート致します。
編集者

-
不動産の共有名義による「相続」「離婚」「相続後」などの親族間トラブルを抱えている方は共有持分サポートへ。当社では弁護士、司法書士、不動産鑑定士、税理士などの専門分野のスタッフが共同で問題解決のために取り組むことで、素早い対応が可能となっております。
本社を置く大阪だけではなく、全国エリアをカバーしており、これまでも遠方にお住まいのお客様の問題解決を数多く対応させていただいた実績がございますので、どなたでもお気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 2026年1月5日相続コラム土地の相続税が払えない場合どうなる?延納や物納制度と土地売却の活用法
- 2025年12月20日共有持分コラム自分に最適な手段を見つける!共有不動産を現金化する方法を解説
- 2025年11月20日相続コラム相続登記義務化と共有持分の影響!罰則内容と登記手続きの変更点を解説
- 2025年11月5日共有持分コラム持分放棄することと登記変更のステップとコスト解説
共有持分不動産の問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
-
お電話での無料相談はこちら
-
-
無料相談はこちら
-
-
-
受付時間
-
10:00~20:00【年中無休】
-