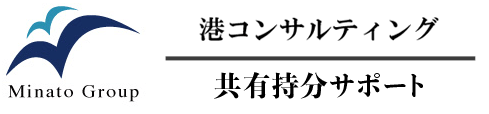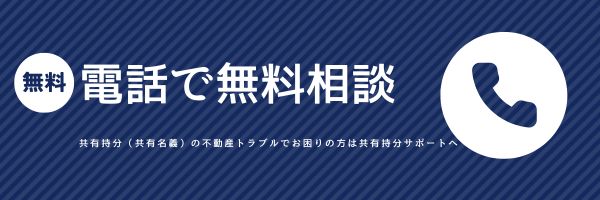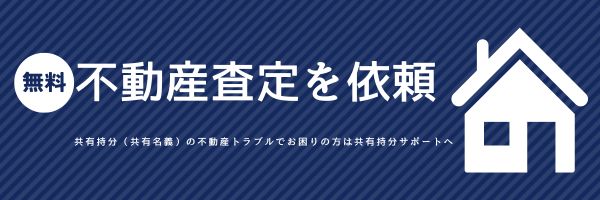-
未登記建物の売買契約と必要書類とは?手続き費用も解説

未登記建物の売買は、通常の不動産取引とは異なる手続きや注意点が多く、戸惑う方も少なくないでしょう。
スムーズな取引を進めるためには、事前に必要な知識をしっかりと理解しておくことが重要です。
今回は、未登記建物の売買契約の進め方、必要な書類や手続き、税金や費用、そしてリスクと対策について解説します。
未登記建物とは?
未登記建物の定義
未登記建物とは、建物を建てた際に法務局へ登記申請をしておらず、建物の情報(所在地・構造など)が登記簿に記載されていない建物のことを指します。
未登記になる原因とリスク
未登記になる原因は、登記を忘れた、費用を節約した、相続後に放置された、などさまざまです。
未登記のままにしておくと、法的な問題が生じるだけでなく、所有権が不明確になり、将来的にトラブルに発展する可能性があります。
未登記建物は売却できるのか
「未登記でも売却は可能なのか?」という疑問を持つ方は多いですが、売却自体は可能です。
売却後に買主が登記を行えば問題はなく、売却方法としては「登記してから売却」「解体してから売却」「未登記のまま売却」の3つがあります。
それぞれに注意点があるため、取引前に理解しておくことが重要です。
未登記建物の売買方法
登記をしてから売却
建物表題登記と所有権保存登記を行ってから売却する方法です。
登記により所有者情報が明確になるため、買主側も安心して取引が行え、第三者に不正に売却されるといったリスクも防げます。
建物を解体してから売却
建物を解体して更地にすることで、登記の必要がなくなります。
ただし、解体には費用や手間がかかるほか、更地にすると固定資産税が上がる可能性があるため、事前にしっかりとした計画を立てる必要があります。
なお、解体後は「家屋滅失届」の提出が必要です。
未登記のまま売却
未登記のまま売却する場合は、売買契約書の特約事項に「未登記建物」であることを明記します。
契約後、買主側が建物表題登記と所有権保存登記を行います。
しかし、買主側にとって登記義務が課される点やリスクがあるため、個人間での取引には不向きです。
不動産会社など、専門の業者であれば買い取りしてもらえる可能性があります。
未登記建物の売買契約の進め方
売買契約書に記載すべき項目
未登記建物の売買契約書には、通常の不動産売買契約書と同様に、売主・買主の氏名・住所、物件の所在地・地番、売買価格、決済日、手付金、引渡し時期などが明確に記載されている必要があります。
加えて、未登記であることを明記し、登記完了までの責任分担や、仮登記の有無、登記費用負担についても詳細に記述しましょう。
特に、境界線や建物の現状、瑕疵担保責任の範囲などについては、具体的な記述と、必要に応じて写真や図面などの証拠資料を添付することで、後々のトラブルを予防することが重要です。
曖昧な表現は避け、明確で具体的な記述を心がけましょう。
手付金の相場と注意点
手付金の金額は売買価格の10%程度が一般的ですが、物件の状況や交渉によって変動します。
未登記物件の場合、登記手続きの遅延や不確定要素のリスクを考慮し、手付金の額や条件について、売主・買主間で十分な協議を行い、契約書に明記することが重要です。
手付金は、契約の履行を確保するための担保として機能するため、契約不履行の場合の効力(違約金としての扱いなど)についても、明確に記載しておくべきです。
また、手付金支払いのタイミングや方法についても、契約書に明確に定め、トラブルを回避しましょう。
売買契約におけるリスクと対策
未登記建物の売買では、境界確定や権利関係の確認が困難であること、登記手続きに時間がかかること、想定外の費用が発生することなど、様々なリスクが潜んでいます。
これらのリスクを軽減するためには、事前に専門家(不動産業者、司法書士など)に相談し、物件調査や登記手続きに関するアドバイスを受けることが重要です。
また、売買契約書には、リスク軽減のための条項(例えば、登記できない場合の契約解除条項など)を盛り込むことを検討しましょう。
さらに、売買契約締結前に、物件の状況を十分に確認し、売買価格や諸費用について、客観的な根拠に基づいた適正な価格設定を行うことも重要です。
未登記建物の売買に必要な書類と手続きは?
売買契約に必要な書類一覧
売買契約に必要な書類としては、通常の売買契約に必要な書類と登記がないことを補うための証明が必要になります。
売主・買主の本人確認書類(運転免許証、保険証など)、物件の所在図、建物図面、売買契約書、重要事項説明書、その他売買に関連する書類などが挙げられます。
未登記物件の場合は、所有権を証明する書類(例えば、建物請負契約書や領収書、建物確認済証、相続関係を証明する戸籍謄本など)も必要となる場合があります。
また、物件の状況を把握するために、現地調査や測量の結果を記録した書類も重要です。
これらの書類は、契約締結前に漏れなく準備しておくことが重要です。
登記申請に必要な書類と手続き
売買後に買主は登記申請が必要です。
まず、建物表題登記を申請します。
これは土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
その後、所有権保存登記を申請します。
これは表題登記を終えた建物を買主名義で保存登記することです。
これで未登記から登記簿上の不動産となります。
未登記建物の登記申請には、以下の書類が必要です。
【建物表題登記に必要な書類】
・建物表題登記申請書
・建物図面
・各階平面図
・所在図
・配置図
・固定資産税評価証明書
【所有権保存登記に必要な書類】
・所有権保存登記申請書
・売買契約書
・所有権証明資料(建築確認済証・検査済証、建築請負契約書など)
・住民票
・印鑑証明書
・法務局への登録免許税
所有権保存登記の申請手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士は、申請に必要な書類の作成や提出、登記申請の手続きを代行してくれます。
申請が受理されると、法務局から登記完了の通知が届きます。
その通知を受け取った時点で、買主が正式な所有者になります。
司法書士への依頼と費用
司法書士への依頼は、登記申請手続きの円滑な進行と、法的リスクの軽減に役立ちます。
司法書士への報酬は、物件の価格や登記手続きの複雑さによって変動しますが、事前に見積もりを取ることが大切です。
報酬以外にも、実費(例えば、郵送費用など)がかかる場合もあります。
未登記建物の売買にかかる税金と費用
売買にかかる主な税金の種類と金額
未登記建物の売買にかかる主な税金は、登録免許税と不動産取得税です。
登録免許税は、登記の申請時に法務局へ納付する税金です。
申請書に収入印紙を貼って納めます。
不動産取得税は、不動産を取得した後に、都道府県から課税される税金です。
取得後、大体半年~1年以内に納税通知書が届きます。
その他、不動産売買にかかる諸費用として、仲介手数料、司法書士報酬、測量費用などが発生します。
登録免許税と不動産取得税の計算方法
登録免許税は、所有権保存登記の場合、固定資産税評価額×0.4%で計算されます。
不動産取得税は、固定資産税評価額×3%(軽減措置もあり)で計算されます。
ただし、税率や税額の計算方法には様々なケースがあり、複雑な面もあります。
これらの税金の計算は、税務署や専門家に相談するのが確実です。
まとめ
未登記建物の売買は、通常の不動産売買よりも複雑な手続きやリスクが伴います。
スムーズな取引を進めるためには、売買契約書の内容を十分に理解し、必要な書類を準備し、専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。
本記事で紹介した情報を参考に、慎重な準備と手続きを進めていただくことで、安心して取引を進めることができるでしょう。
未登記のまま相続した建物でお困りでしたら、当社でもご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
編集者

-
不動産の共有名義による「相続」「離婚」「相続後」などの親族間トラブルを抱えている方は共有持分サポートへ。当社では弁護士、司法書士、不動産鑑定士、税理士などの専門分野のスタッフが共同で問題解決のために取り組むことで、素早い対応が可能となっております。
本社を置く大阪だけではなく、全国エリアをカバーしており、これまでも遠方にお住まいのお客様の問題解決を数多く対応させていただいた実績がございますので、どなたでもお気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 2026年2月20日共有持分コラム共有不動産の査定で見るポイントとは?価値を決める要因を解説
- 2026年2月5日共有持分コラム共有名義の不動産で片方が死亡したら誰が相続する?
- 2026年1月5日相続コラム土地の相続税が払えない場合どうなる?延納や物納制度と土地売却の活用法
- 2025年12月20日共有持分コラム自分に最適な手段を見つける!共有不動産を現金化する方法を解説
共有持分不動産の問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
-
お電話での無料相談はこちら
-
-
無料相談はこちら
-
-
-
受付時間
-
10:00~20:00【年中無休】
-