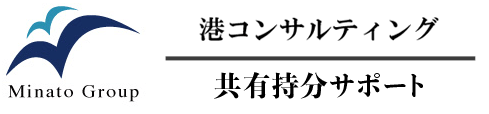-
親族と共有名義不動産・認知症によるリスクと解決策
高齢の親と不動産を共有している場合、いつか訪れるかもしれない親の認知症、そしてその後の不動産売却について、不安を感じているのではないでしょうか。
認知症になると、ご自身の意思で財産を処分することが難しくなります。
そのため、現状のままでは、いざという時に不動産をスムーズに売却できない可能性があります。
今回は、認知症の親族と共有名義の不動産を所有する際の法的リスクと、それに対する具体的な対策を解説します。
認知症の共有名義人がいる場合の問題点
共有不動産の売却には、共有者全員の同意が必要です。
しかし、認知症の親族が意思能力を欠いている場合、その同意を得ることが困難になります。
意思能力のない人が行った売買契約は無効となる可能性が高く、売却手続きは滞ってしまうでしょう。
仮に、他の共有者が親族の代理として契約を結んだとしても、その契約が後に無効とされるリスクがあります。
認知症の親族と共有名義の不動産を売却するには?
成年後見制度の活用
成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった人の財産を守るための制度です。
家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の代わりに財産管理や法律行為を行います。
制度には2種類あります。
1.法定後見制度
すでに認知症を発症している親族が対象です。
家族などが家庭裁判所に制度の申し立てを行います。
そして裁判所が選任した後見人が、本人の財産管理や身上保護などを代行します。
判断能力の程度により、後見人が関与する範囲は異なります。
2.任意後見制度
判断能力がある状態のうちに、今後の備えとしてあらかじめ支援内容や後見人等を自分自身で決め契約を締結しておく制度です。
実際に認知症などで支援が必要になった際にサポートしてもらいます。
3.成年後見制度の注意点
後見人の選任には時間と費用がかかり、手続きが複雑です。
後見人は自由に選べ図、裁判所が選任します。
後見人の選任は本人の死亡まで継続されます。
※後見人が高齢・病気・引っ越しなどの事由での辞任はありますが、その場合は新たに後見人が選任されます。
法定後見人による売却
裁判所の許可を得たうえで、法定後見人の権限で不動産売却を行うことができます。
ただし、本人の利益を最優先して審査されるため、家族の都合だけでは売却が認められない場合もあります。
売却の必要性が不明確、価格が相場より低いなどと判断された場合は申請が却下されるケースもあります。
自分の持分だけを売却
認知症の親族が共有者である場合でも、他の共有者は自分の持分を自由に売却できます。
他の共有者の同意は必要ありません。
そのため、共有関係から抜けたい場合は、自身の持分のみを売却するという方法も検討できます。
ただし、共有持分のみの売却は、全体を売却するよりも一般の方の買い手がつきにくく、価格も低くなる可能性があります。
共有持分を専門に扱う不動産業者に相談することで、スムーズな売却につながる可能性があります。
当社では共有持分専門の買取サービスを行っています。
まずはご相談ください。
認知症になる前にできる事前対策
共有名義であるがゆえに、自由に活用できないというリスクがあります。
そのために、判断能力があるうちに共有名義を解消しておくことでリスクを未然に防ぐことができます。
生前贈与
生前贈与とは、生きているうちに財産を贈与することです。
認知症になる前に、親族に不動産の持分を贈与することで、将来の不動産売却に関するトラブルを回避できます。
1.メリットとデメリット
メリットは、贈与後に自由に売却できるようになることですが、デメリットとしては贈与税が発生すること、贈与によって相続財産が減ることなどが挙げられます。
2.税金対策
生前贈与によって贈与税が発生する可能性があります。
贈与税の額は、贈与額、贈与者の年齢、贈与相手との関係などによって異なります。
税金対策として、「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらを選択するかが重要になります。
それぞれの税制の特徴を理解し、状況に合った方法を選択する必要があります。
税理士に相談して、最適な方法を選択しましょう。
※年間110万円までの基礎控除を利用する「暦年課税」方式
※最大2500万円まで贈与税がかからない「相続時精算課税」方式
3.贈与契約の注意点
贈与契約書には、贈与する財産、贈与する相手、贈与の時期などを明確に記載する必要があります。
契約書の作成は、専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。
契約内容に不備があると、贈与が有効にならない可能性があります。
また、贈与は、贈与者の意思能力が十分にある状態で行う必要があります。
認知症リスクのある親族から持分を買い取る
認知症になる前に、共有持分を親族間で売買し、名義を整理する方法もあります。
たとえ親族間でも、売却価格は相場に沿った価格にしないと「みなし贈与」として贈与税が発生する可能性があります。適正価格での売買取引をしましょう。
任意後見契約による備え
前述しましたが、任意後見契約とは、本人が将来のために、後見人や支援内容等を自分で決め、自分の判断能力が不十分になった際にサポートしてもらうという制度です。
事前に共有名義を解消する手段ではありませんが、支援内容等を決める際に、不動産の売却に関する取り決めも行っておくことで対策できます。
まとめ
認知症の親族と共有名義の不動産を所有する際には、全体売却をしたい場合でも同意を得ることが難しい為、困難になります。
成年後見制度の活用、共有持分の売却、生前贈与など、様々な対策が考えられますが、それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、手続きも複雑です。
状況に応じて最適な対策を選択するためには、弁護士や司法書士、税理士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。
早めの相談が、将来のトラブルを回避し、安心した老後を送るための第一歩となります。
事前に専門家と相談し、適切な対策を講じることで、将来起こりうる問題を未然に防ぎ、安心できる未来を築きましょう。
特に、認知症の兆候が見られる場合は、早急な対応が求められます。
当社では共有持分の不動産についてのサポートを行っています。
共有持分の不動産にお困りでしたらお気軽に当社にご相談下さい。
編集者

-
不動産の共有名義による「相続」「離婚」「相続後」などの親族間トラブルを抱えている方は共有持分サポートへ。当社では弁護士、司法書士、不動産鑑定士、税理士などの専門分野のスタッフが共同で問題解決のために取り組むことで、素早い対応が可能となっております。
本社を置く大阪だけではなく、全国エリアをカバーしており、これまでも遠方にお住まいのお客様の問題解決を数多く対応させていただいた実績がございますので、どなたでもお気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 2026年1月5日相続コラム土地の相続税が払えない場合どうなる?延納や物納制度と土地売却の活用法
- 2025年12月20日共有持分コラム自分に最適な手段を見つける!共有不動産を現金化する方法を解説
- 2025年11月20日相続コラム相続登記義務化と共有持分の影響!罰則内容と登記手続きの変更点を解説
- 2025年11月5日共有持分コラム持分放棄することと登記変更のステップとコスト解説
共有持分不動産の問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
-
お電話での無料相談はこちら
-
-
無料相談はこちら
-
-
-
受付時間
-
10:00~20:00【年中無休】
-